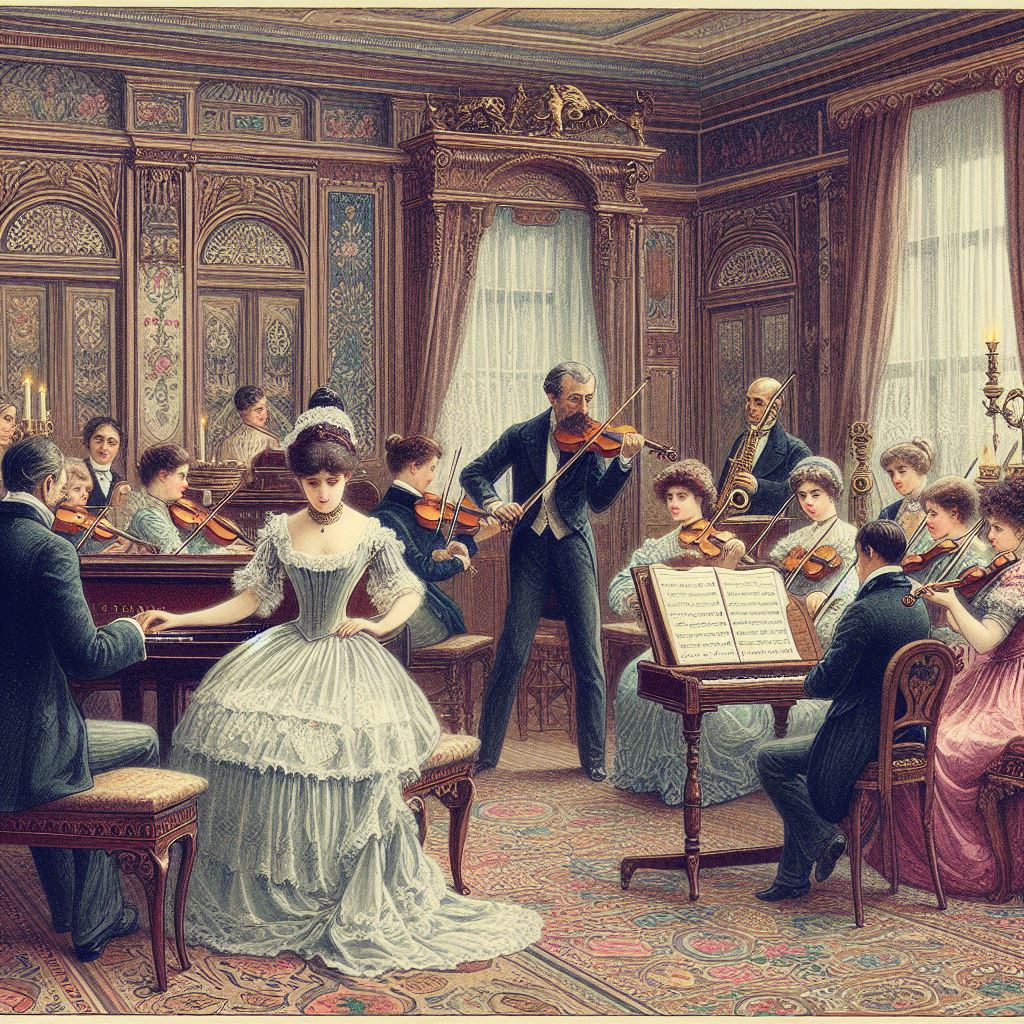芭蕉 は江戸に旅立つ門人にはなむけとして、次のような俳句をひねりました。
梅若菜丸子の宿のとろろ汁 猿蓑
新春の道中には、梅もある、若菜もある。丸子の宿(静岡市 内)ではおいしいとろろ汁が待っている。色彩豊かで味覚まで刺激されます。芭蕉 の弟子を励ます気持ちが伝わってきます。
この名句ほど素敵で心温まる食の列挙はできません。でも、貧しい食体験からでも、私なりのめずらしい<お手頃フレンチづくし>を試みてみましょう。
ロンバルディア州 の代表的なイタリア料理の一つで、骨付き仔牛すね肉を厚さ4cmの輪切りにし、トマト、白ワイン、スープ、味付けした野菜、グレモラータで煮込みます。骨のズイにはコラーゲンがたっぷり!イタリア語で、オッソは「骨」で、ブッコは「穴」です。
https://www.thehouseofelynryn.com/2021/12/01/steak-au-poivre/ ステーキ・オ・ポワブルは、粗挽き黒胡椒とコニャックをたっぷり使ったソースを添えたペッパー・ステーキです。 フライパンでフィレ・ミニョン(牛ヒレ の先の部位)を焼きます。 ビフテキ に飽きた時などにいかがでしょうか?もっとも、フランスの牛肉には脂身が少ないので、飽きが来ることはありません
https://www.cuisineaz.com/recettes/raie-au-beurre-noir-29028.aspx 美しいエイヒレ 、ソース用のバター、酢、そしてニンジン、タマネギ、ケイパーを添えて。「エイなんか食べられるのか」と思われるかもしれませんが、エイの肉は、柔らかく厚く、そこに焦がしバターが程よくしみて美味です。フランスは山の幸だけではなく、海の幸にも恵まれた国です。食材は多彩で、とても豊かです。日本とフランスの食料自給率 は、それぞれ、38%と125%です。
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_aux_noix 胡桃入りのチーズ くるみチーズはフランス産のチーズです。ナッツで飾られたプロセス・チーズで、特に年末に食べられるサヴォア (イタリア国境)の名物です。サヴォワ 地方には、フォンデュというよく知られた料理もあります。これは、硬くなってしまったパンをチーズと一緒に溶かして食べたことから考案された料理で、日本でも一時期広まりました。
メレンゲ が特徴です。 日本人にふるまうと、とても喜ばれます。作り方はとてもカンタン!
フランスでは、日曜の昼食に招かれることが珍しくありません。長い時間をかけて、食事を、会話を楽しむためでしょう。最後のコーヒーが出て来るのが 四時になることもあります。そういえば、「食卓の愉しみ」という表現も使われます。食卓の名人のような人もいて、その人はよく食べ、よく飲み、よく味わい、よく話し、よく人の話の真意までも聞き取りますが、それだけでなく、話の合間に自分の意見を巧みに手短に表現します。長い食文化・歴史から生まれるタイプの人と言えるでしょう。偏らない豊かな知恵が日常のテーブルで発揮されます。そんな達人級の会食者と同じテーブルを囲むと、味覚の楽しみとともに、それはとても深い記憶になって残ります。素晴らしい土産話にもなることでしょう。
そうそう、食後には、アイザック ・ディーネセン原作の名作映画「バベットの晩餐会 」(デンマーク 1987年)などいかがでしょうか。デンマーク の寒村の牧師の信心深い二人の娘は、生きたウミガメやウズラに肝をつぶして、口にしようとしません。しかし、次第に、料理の魅力によって・・・。この名画には、「失われた時を求めて 」で引用される、当時の有名なパリのレストラン 「カフェ・アングレ」の女性シェフ「バベット」が主役をつとめ、そのすぐれた料理の腕前でもって、互いに硬く閉ざしていた会食者たちの心をほぐしてゆきます。グルメ映画ではなく、より深い人間的な訴えが秘められています。
≪番外編≫
めいたがれいの「エイヒレ の焦がしバターソース添え」仕立て 本編のメニューのうち、日本では普段手に入りにくい、エイヒレ の代わりにめいたがれいを使って「エイヒレ のソテー焦がしバターソース添え」仕立てをつくってみたところ、たいへん美味しかったので、番外編としてレシピをご紹介します。お魚は白身 のすずきや鯛でも良いと思います。 是非、フランスの味をお試しください。
【材料】(2人前)イタリアンパセリ (又は万能ねぎの小口切り)適量
【作り方】イタリアンパセリ を加えて良く混ぜる。
焦がしバターソースが上手にできるとまるでバタースカッチのような香ばしさ。ソースの染みた魚も付け合わせの野菜もなんともいえない美味です。
編集協力 KOINOBORI8
にほんブログ村