Ⅲ.ゲルマント公爵家と主人公の変貌 「失われた時を求めて」 対話的創造性のほうへ 3/4
この長編小説では当初主要テーマとして照明を浴びて舞台前面を占めていたパリ社交界や恋愛模様が、読み進むにつれやがて少しずつその重要性を薄めてゆきます。反対にそうした全般的な流れに逆らうようにして、それまで目立たなかった脇役たちが舞台の袖から中央へと登場してきます。長く主役をはってきたものは翳り、それに代わりそれまで出番も少なく、役割も明確ではなかった端役たちが互いに関連を持ち始め、新たな役回りも得て、作家志望の主人公を創作へと導きます。
以下のⅢ章では、まず19世紀から20世紀に移る端境期のパリ貴族階級で起きる大きな変動を描きます。また、それとともに間欠的に起きる主人公マルセルの内面における大きな変化も明らかにします。主人公は大きな社会変動に巻き込まれるし、恋愛においてもアルベルチーヌへの嫉妬に苦しみ、ペシミックな思いを深めることになりますが、最後には周囲のさまざまな声にうながされて、創作のためのペンを執ることを決意します。
社交界の中心となるのは、なんといってゲルマント公爵家です。長編小説前半では、王家とも姻戚関係を結ぶ公爵一族の権勢に富む生活が描かれます。しかし、次第に公爵家の型にとらわれた生活に宿る狭さや脆弱さがあばかれるようになります。小説後半では傾き始める一族の実態が残酷ともいえる筆致で描かれます。たしかにこの小説には20世紀初頭のおいて実際に起きたフランスの貴族階級の決定的な凋落や、それに入れ替わるように台頭する新興ブルジョワジーの繁栄ぶりも描かれます。
しかし、「失われた時を求めて」は階級社会を批判するレアリスム小説ではありません。社会風俗はこの小説ではかなり誇張して描かれています。大ブルジョワのヴェルデュラン家による浪費は、当時のフランスではまずありえない話です。当時、フランスでは金融や土地の価格が乱高下を繰り返していて、富裕層でも誕生日に宝石を贈ったり、バカンスに高級リゾート地のお城を毎年借り出すほどの金銭的余裕など持てなかったはずです(ジュリアン・グラック「終着駅としてのプルースト」)。
まず、傾き始める以前の華やかなゲルマン公爵家の生活が、主人公が春の休暇を過ごす、パリから南西へ約100キロ離れたコンブレという小さな町の生活と対比されながら描かれます。公爵家はコンブレの教会内に6世紀以来の領主として私的礼拝堂を構えていて、その不可侵性を「父なる神」であるかのように誇ります。公爵の弟シャルリュス男爵のほうも、爵位の称号だらけの家系図をえんえんとたどってみせては、自分の家系を高貴な血統だなどと言い、自慢話の独演にふけります。第5篇「囚われの女」でも、コンサートが催される富裕層ブルジョワのヴェルデュラン夫人のサロンに乗り込んだシャルリュス男爵は、演奏されるヴァントゥイユの7重奏曲を「偉大なる大芸術」などと大袈裟に例えてみせては、「司祭」よろしくその場を我が物顔で取り仕切り、ついに自分のサロンを「音楽の殿堂」と称して貴族階級に伍そうとしていたヴェルデュラン夫人の怒りを買い、同性愛者との仲を引き裂かれ、サロンから締め出されます。
しかし、コンブレの教会は、そこに料理女フランソワーズやサズラ夫人やテオドールといった町民たちが出入りし、聖人たちの彫像群と親しげに話を交わし、教会が人が住める生活のための「住居」のような様子を見せ、また町民たちも教会に共感を抱くようになる時にこそはじめてその魅力を発揮します(ブログ記事「「失われた時を求めて」の文はなぜ長いのか」(2022・4))。
公爵はゲルマント家はヨーロッパ中に広がる高貴な家柄の起源となっているなどと主張しますが、しかしその起源の場所たるやじつはコンブレのはずれのひなびた共同洗濯場でしかありません。そもそも、プルーストは家系図のように、時系列の経過を連続体として把握し、理解しようとすることを嫌っていました。「失われた時を求めて」のタイトルを当初は「心情の間欠」にしようと構想していたことからも理解できるように、彼にとって時間は一定の間を置いて、断続的に進むものでした。いわゆる無意識的記憶も小説全編に渡って間欠的にしか起きませんし、主人公も巻末で自分は「間欠的な人間」であることを意識します。
こうしてゲルマント公爵家とコンブレの街の素朴な生活は対照的に対置させられてゆきますが、公爵家の生活よりもコンブレの町の生活のほうが実は精彩に富んでいるし、その後の小説の展開により深く関わってくることが暗示されます。一方、ゲルマント公爵家の一見華やかな日常がその下には伝統墨守の頑迷さや虚栄心を隠していて、開かれるサロンにおいては対話もしばしばギクシャクしたものになります。
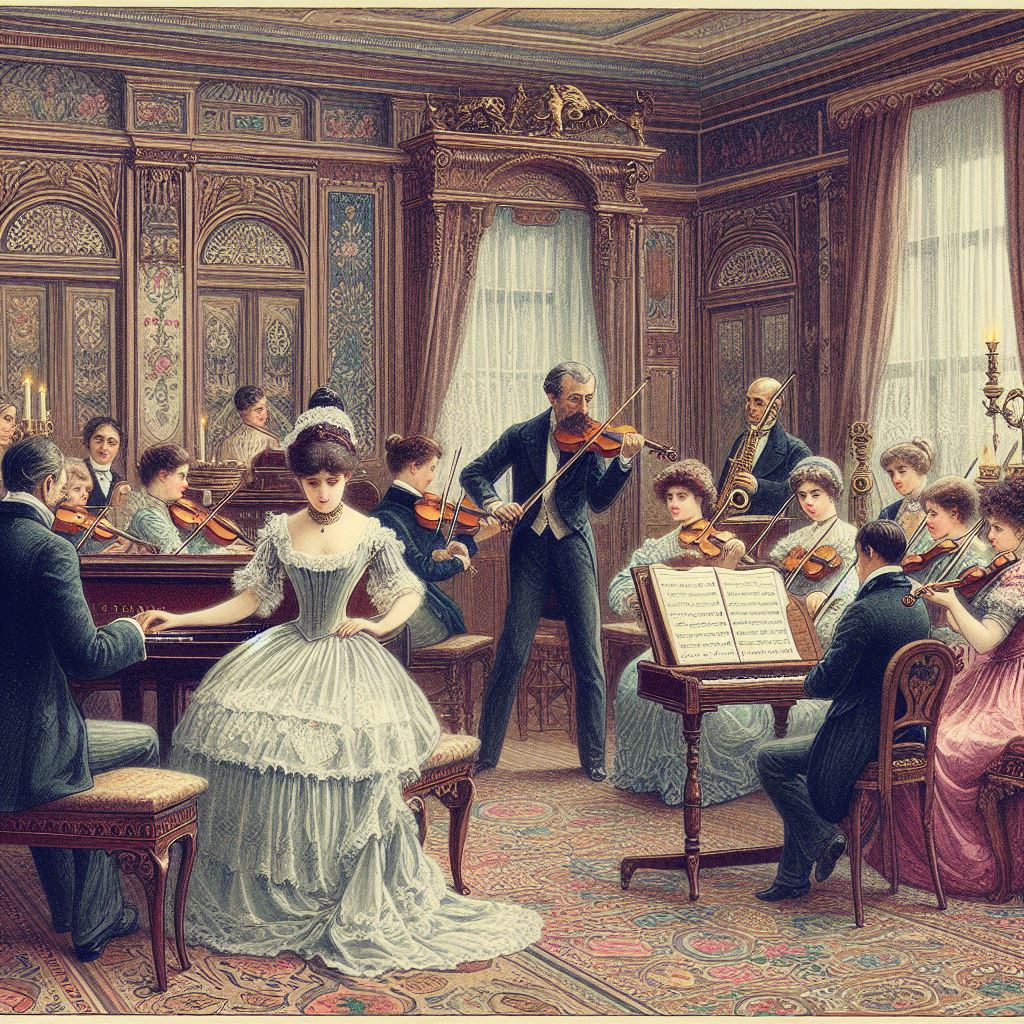
第3篇「ゲルマント家のほう」で主人公一家はコンブレからパリ中心の貴族街サン=ジェルマンに引っ越し、ゲルマント公爵家の館とは中庭をはさんだ正面にあたるアパルトマンに住み込みます。コンブレで見かけて以来、あでやかで美しい公爵夫人に憧れる主人公は、そのサロンに招き入れられ、古い民謡の響きの混じる夫人特有の発音や才気をひけらかす発言に長いこと魅了されます。しかし、次第に夫人の故意に俗っぽい口調で言い放つ機知に富む警句が、公爵夫人のしきたりにとらわれない自由な知性に基づくものではなく、引き立て役の夫の公爵や取り巻きに乗せられたものであることに気づきます。公爵夫人にも一族特有の霊が取り付いていて、家名に傷がつくと判断するやいなや、ざっくばらんな態度をたちどころに硬化させ、無愛想で横柄になります。女優ラシェルが世間で評判をとるや、彼女の才能を見出したのは自分だとばかり公爵夫人はラシェルをサロンに招きはします。しかし、そのユダヤ人女優にゲルマント公爵家の基準に照らして容認できない点があると見てとると、今度は公爵夫人はたちまちラシェルの朗誦の才能を否定し、「ラシェル」という芸名ではなく「あの子」と侮蔑的に呼び、サロンから排斥してしまいます。主人公は最後には公爵夫人の皮相で偏った芸術受容に失望し、怒りをおぼえるようにもなります。パリの大きな館には蔵書が並べられたプライベートな図書室が設けられていることがあり、公爵家の館もその例にもれませんが、公爵夫人の知性は、「豪華絢爛たる城館」内に構えられた「時代錯誤で不完全」な「知性を育むことができない図書室」にたとえられることにもなります。
サロンで親密さを誇示しようとしてガラルドン侯爵夫人は、ゲルマント公爵夫人(当時はレ・ローム大公妃だった)に「オリアーヌ」とファースト・ネームで呼びかけますが、公爵夫人は自分との親密度を誇示するその態度を馴れ馴れしすぎると感じ、答えようとはしません。爵位のついた重々しい苗字で呼ばれるのがお好きなのです。このため、公爵夫人は、爵位に執着するあまり、ガラルドン侯爵夫人宅で開かれるモーッアルトのコンサートへ招かれる機会を自ら失うことになります。ファースト・ネームで呼ばれて、芸術受容へと導かれる主人公とは対照的な態度です。
一方、主人公の書棚の本のほうは、アルベルチーヌや使用人によっても借り出され、読み込まれていて、彼の書棚のほうは知的刺激を与える開放的な場として活用されています。貧しい孤児であった恋人アルベルチーヌも主人公の書架に置かれていたドストエフスキーを読み込み、画家エルスチールや作曲家ヴァントゥイユからも多くのことを学び取り、精神的な成長をとげてゆきます。主人公の書棚は、公爵家の豪華な蔵書が眠る閉塞感漂う図書室とは対照的なものです。なお、プルーストは、ドストエフスキーの小説「白痴」を書簡において非常に高く評価してします。
本に書かれている巧みな言い回しをすぐに身につけ口にするチョッキ仕立て職人ジュピアンとは異なり、暗記することができない公爵は、社交界での声望を自ら高めようとして気の利いた文をメモに書きとめ、それをサロンで読み上げる機をうかがいます。女性蔑視の、またドレフュス事件の際は人種差別の発言も口走ります。隣人の主人公の祖母が重体に陥ったときは、隣人として見舞いに来ますが、早すぎるお悔やみを悲しみに暮れる主人公一家を前に口にしてしまい、社交喜劇をひとりで演じてしまいます。祖母は公爵のことをのちに一言で評します、「俗っぽい方」と。
自分はパリの由緒ある男爵だから本当はより高位の爵位の貴族だなどと主張するシャルリュス男爵は、親しい友人スワン ― 一部は若い頃のプルースト自身 ― と同様、偶像崇拝という狭い受け身の芸術受容を繰り返します。男爵はバルザックの革製装丁本をフェティッシュに愛蔵し、何かというと「それははなはだバルザック風ですな」などとバルザックになりかわってひとりごちます。しかし、結局のところスワンと同じような「芸術の独身者」にとどまり、作品の字義通りの受容だけで満足し、深い呼びかけやうながしを作品から聞き出し、そこから自らの真の個性を涵養し、それを他者に向かって表現することができません。なるほど主人公は才分に恵まれたシャルリュス男爵が執筆活動に打ち込むことを望みはしますが、期待されるのは「無尽蔵の目録」や「生彩にまったく欠ける連載小説」でしかありません。
シャルリュス男爵はサロンで傍若無人にスカトロジックなことを口走りますが、その時主人公はその傲岸不遜な態度に怒り、男爵のシルクハットを踏みにじるようになります。同性愛者シャルリュス男爵は最後は苦痛常習者のようになり、かつて愛した美貌のバイオリン奏者モレルに似た男娼に鞭打たれる快楽を追い求めるようになります。尊大でサディスティックな態度はマゾ的な姿勢へと反転します。プルーストは男性の倒錯者には女性が潜んでいると考えていました。そして世界ではじめて空爆にさらされる第一次大戦下のパリの夜をさまよいます。欲望に駆られ、快楽に依存する「地獄めぐり」(バンジャマン・クレミュ「見出された時」)の様相が描かれます。

小説巻末では、こうしてゲルマント公爵家内外に暗い闇がたれ込めます。ゲルマント大公夫人邸の午後の集い(マチネ)に久しぶりに足を踏みれた主人公マルセルには、社交界人士が老いという「仮装」をしているように見え、驚きます ― 嵐に打たれる岩のような面貌と化した公爵、地層学的なまでの深いシワに刻まれた貴族、声によってしか見分けがつかなくなった旧友・・・・。今や時間による侵食作業がいたる所で進行しています。ゲルマント大公は老い、最高級の、しかし閉鎖的なジョッキークラブ会員にも選出されないし、貴族の街サン=ジェルマンの「居城」も手放さざるをえなくなっています。公爵の歩行は困難になり、よろめき、鐘楼よりも高い竹馬もろとも転落しそうです。爵位というハードルは低くなり、大ブルジョワのヴェルデュラン夫人は三度目の結婚でいつのまにかゲルマント大公夫人におさまりますが、相変わらず派閥作りに余念がありません。爵位の継承にはどこか「悲しいもの」が感じられると最終篇「見出された時」に書かれているし、また人物の性格と同じように社会もその固定した像を示すことは不可能だ、性格も社会も時間とともに変化するという文が第五篇「囚われの女」に書かれています。
驚くことに、そのサロンにはコンブレの教会を住居に変容させてみせてみせたサズラ夫人も来ています。貴族の街サン=ジェルマンに「民衆的」で「田舎風」の生活までが入り込もうとしています。主人公が寄稿した記事が「フィガロ」紙に掲載された時、公爵は雄弁な賛辞を筆者の主人公に送ってきますが、その文面の表現は、コンブレの素行不良の食料品店の青年テオドールから送られてきた賛辞の表現よりもつたないものでした。すでに第3篇「ゲルマントのほう」には次のような文が予告のように書かれています ― 「当時のゲルマントの名は、酸素なり別の気体なりを封じ込めた小さな風船のようなものだ。それを破って中の気体を発散させれば、私にはその年その日のコンブレの空気を吸うことができる」。パリという中央とコンブレという周縁との上下関係が確たるものではなくなり、反転しそうなのです。
社会が大きく変動し、旧弊が消滅へと向かう時代の転換期の凄みに富んだ描写が続きます。しかし、この小説は社会という壁画を再現するだけでは終りませんし、主人公マルセルは社会の端境期に立ち会うだけのただの傍観者でもありません。しばらく前から読者はこうした動揺する厳しい現実に接しながらも、まだこれから何か重要なことがマルセルの内面で起きるはずだと思うはずです。
そういえば、最終篇「見出された時」にはプルーストが愛読する「千一夜物語」がしばしば引用されます。このアラブの物語では、主人公シェーラザードは語り始めることによって自らを生命の危機から救い出します。作家志望の、しかしすでにかなりの年齢になった主人公マルセルも、ゲルマント大公夫人邸私設図書室の中で、小説冒頭のコンブレの就寝劇で母親によって朗読されたジョルジュ・サンドの小説「捨て子フランソワ」を見つけます。マルセルは母の創造的な読み聞かせの実践を、今度は自ら語り手に変身した姿となって行おうと決意します。母は朗読をヴァントゥイユの曲に乗せるようにして行い、身をもって創意に富む読み聞かせを実践したのです。主人公に向かって創意を表現することによって、まだ幼かった主人公に創造的な反応を引き出そうとしていたのです。
直前に3回も繰り返し体験した無意識的記憶によって、最終篇巻末のパリのゲルマント公爵家図書室から第1篇冒頭のコンブレという過去へと遡る流れがすでに切り開かれ、準備されています。いよいよそのコンブレで小説を読み聞かせてくれた母親にうながされる形で、マルセルは最後に母親と交代し、今度は自らが創意を発揮して語る主体になろうと決意します。そして母や、母の分身である祖母や、祖母の死後に恋人になるアルベルチーヌ、またコンブレの人々をたんに忠実に回想し、写実的に再現するのではなく、彼らの創意にうながされる形でそうした過去に新たな意味を与えて再創造しようと決意します。「自分に湧いてくる感覚を薄暗がりから出現させ、それをある精神的等価物に転換するようにしなければならない」(「見出された時」)。
つまり、コンブレの就寝劇で母親が行った創造的な朗読を自分なりに受け継いで、過去に新たな意味を与えながら過去を救い出そうとします(ジュリア・クリステーヴァ「想像界」「プルーストと過ごす夏」所収)。また、ジル・ドゥルーズも書いています ― 「想起することは、創造することであり(・・・)、構成された個人の外側に飛び出す」ことだ(「プルーストとシーニュ 増補版」)。
ゲルマント公爵家に対して幻滅をおぼえますし、その個人図書室は深い沈黙に包まれています。しかし、母だけでなく、多くの声にうながされる主人公マルセルは失望をおぼえつつも、表現という創造に取り掛かろうと決意します。「一見完全に幻滅し切ったように見える一つの作品を、実は歓喜が支配している」(L・マルタン=ショフィエ「プルーストと四人の人物の二重の<私>」)。新たにマルセルと名付けられた主人公は、語り手となって、過去に架橋をかけ、過去に新たな意味を付与しようとします。自分に何かを始めることができることを意識します。それまで断片的に断続的にしか聞こえてこなかった声は、互いに交響するようにつながり、その精彩に富む大きな流れは、マルセルを突き動かします。
閉塞感の深まるゲルマント公爵家のサロンにあって人は孤立し立ちすくみますが、その中にあっても主人公マルセルは、創意に富む言葉によって過去を豊かに再現しようとします。母親や、祖母や、祖母の死後にはアルベルチーヌなども実は創造的表現を行いますが、そうした相手に能動性をうながすような呼びかけに応える形で、ここで主人公マルセルは語り手になることを決意し変貌します。それまでは創作を書こうとして自己中心立場から意思し望んで空回りしてきたのですが、マルセルはここで自分が描くことが他者たちから期待され、また待たれていることを理解します。他者たちから自分に課せられてきた度重なる要請に応えようと決意します。
ここでは大きなドラマが起きています。アリストテレスは、話がクライマックに達するのは、もっとも優れた「再認」と、「逆転」が同時に起きる場合だと規定しましたが(「詩学」)、この場面でもマルセルはそれまでその意味が認知することができなかった母親たちからの声をようやくはっきりと認知し「再認」します。この再認は同時にそれを機に華やかさを誇ったパリの失墜するゲルマント公爵家とコンブレの母親を含む住民たちの立場が「逆転」することを意味します。失望を重ねてきた主人公も「マルセル」と名付けられていましたが、ここでこれから執筆に励む語り手として「逆転」した立場に決定的に立つことになります。成り行きは逆転し、これまでとは反対の方向へ向かって展開されるのです。
なお、小説冒頭の就寝劇のあとに、紅茶に浸したプチット・マドレーヌ菓子を口にした主人公は無意識的記憶に不意に襲われ、喜びを味わいます。有名な場面です。しかし、この時の無意識的記憶はまだ十分には説明されないし、主人公マルセルがおぼえた高揚感も、孤立した一時的なものです。むしろ、その時、この無意識的記憶は甦ってはくるものの、その途中で消えそうにもなります。この時、記憶は「徐々に力を失ってゆく」。マルセルは「深刻な不安」さえおぼえます。「探求? それだけではない。創造することが必要だ」と言います。この時点では、彼はまだ最終篇のゲルマント大公夫人邸で無意識的記憶によって習得する創作のヴィジョンを十分には自分のものにはしていなかったのです。ですから、出来事としては劇的ですし注目される場面ではありますが、まだ「創造する」ための力をまだ習得していなかったのです。主人公はまだ「不安」さえおぼえています。機はまだ熟してはいなかったのです。
したがって、巻末のマルセルと巻頭の母親は合わせ鏡のように向かい合い、創意を表現する対話を交わすかのようになります。たんに対等な関係によって結ばれるコミュニケーションとしての対話だけではありません。意思疎通や相互理解だけが行われるのでもありません。互いは相手をより高いレベルの創造性という能動へと時間をかけてうながします。巻末と巻頭は向かい合い、読者は今まで流れてきた長い時間をパノラマのように一望のもとに収めることになります。
「失われた時を求めて」巻頭の文「長いあいだ、私は早くから床についた」の動詞には、単純過去ではなく、複合過去形が使われています。これを単純過去形にしてしまうと、過去は現在の関心から切り離されて対象化されてしまうし、文は過去の客観的記述になってしまいます。しかし、動詞を複合過去形にすると、過去の出来事と現在との両者のあいだには「生きた関係(エミール・バンヴェニスト「一般言語学の諸問題」)が打ち立てられます。巻頭で母から発信された創意を、巻末においてマルセルはただ思い出し受信するだけでなく、母に応えてそれを自らの創意によって、母を、またコンブレを再創造します。こうした過去と現在のあいだの共感に満ちた「生きた関係」は、やはり書き言葉に使われる単純過去形でなく、原典にあるような口語に用いられる複合過去形の動詞のほうが十全に表現することができるのです。
こうして、「失われた時を求めて」は、作者の全知全能性や独我論的記述や人物の性格や名前の不変性に基づいて構成されることの多かった近代小説に、多彩で豊かな表現の可能性をもたらしました。とりわけ創造の可能性が作者の個我からではなく、対話的な関係性からも生起することを教えてくれるのです。
編集協力 KOINOBORI8