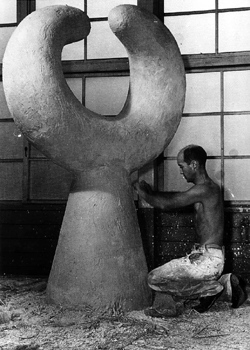東京からようやくキャンプ場に着く。友人Kの小さなワンボックスカーのカーナビが不調で、長野県に入ったあたりか、ディスプレイのマップが突然真っ白になる。道案内の標識を誤読して大回りする羽目になり、夕方遅くになってやっとテントにたどり着く。
あたりはすでに薄暗い。夜が迫っていて、目の前の池も月を浮かべて鈍い銀色だ。釣りはもうできない。北アルプス連峰はすでに姿を消している。四方の低山が黒々と盛り上がり、豚の背に見える。峠近くの冷気が肌を通して浸みてくる。周りのサイトに人はいない。東西南北の方位がわからない。見上げると、夏の主役の白鳥座が天の川の上に大きな翼を広げている。その深い羽音が想像される。流れるような風に吹かれているうちに、長旅による緊張が少しずつほぐれてゆく。
Kがさっそくヘッド・ライトを渡してくれる。Kはほぼ半世紀ぶりに東京の路上でばったり再会した幼な馴染みだ。会社勤めを終え、今では奥さんとふたり暮らしをしているが、十五年前に癌で女房を亡くした元図書館司書のわたしのことを気遣ってくれたのだろうか、人里離れた峠近くでのテント一泊にわたしを誘ってくれた。ヘッド・ライトを着けて歩いてみる。手探りをするようにしか歩けない。まるで遊泳する宇宙飛行士だ。そんなわたしを見ても、Kは少し笑うだけだ。ふたりとも寡黙でも饒舌でもなく、互いを距離を置いて認め合っている。人の心理を詮索しないし、相手に過度に干渉することもしない。
キャンプのベテランKはテキパキと支度を始める。焚き火の火もおこすが、着火も巧みで速い。わたしは下働きに徹するが、時々ヘマをやらかす。暗闇のなかでは足元が特に暗いので凸凹には注意したが、地面に転がっていた玉ネギに気づかず、それを思いっきり踏んづけてしまう。踏み剥がされたひと玉のネギからは、驚くほどの香りが、内部の水分とともにはじけ出てくる。香りは、近くの火に煽られ、まっすぐ立つように広がり、鼻を刺激する。ネギはこんなにも香るのか。「柚子存在す爪たてられて匂うとき」、加藤楸邨の句が浮かぶ。
Kもわたしも、社会のなかでささやかながら与えられた役割を演じてきた。組織や制度がたくみに設けてくれた舞台に立ち、そこで編まれる人間関係をそれなりの良識や熱意でもって生きてきた。もちろん失敗も犯したし悔いも残るが。しかし、そうして運営される舞台から降りて、時間もたってみると、心身の衰えを感じ始めると同時に、今度は今まで送ってきた日常生活には縛られない世界、気づくことなく見過ごしてきた世界に触れてみたいという気持ちに駆られはじめた。曖昧で不可解なものとして排除してきた未知の不思議な領域がどこか生活の周縁、境界を越えた向こう側に広がっているはずだ・・・。
今のうちだ。終わりの始まりが、明日にでも不意にやってくるのだ。衰弱の底に突き落とされる日がドアのベルを鳴らす前に、ただ習慣に従って受け付けてこなかったもの、摩訶不思議なものとして避けてきたものに触れてみてみよう。奇妙で珍奇なものと見なしてきたものとの出会いが、皮膚のように硬く鈍くなった感受性を柔軟にしてくれるかもしれない。狭いマンションから出て、場所をすっかり変えてみれば、鈍くなった感覚でも潜んでいる驚くようなものを感知できるかもしれない。
しかし、この歳になって、肉体的衰えや潜在的な不機嫌や順応力欠如を自覚することなく高揚感を探そうなどと思い立ってみたところで、せいぜい幻滅や苛立ちをおぼえるのが関の山になるはずだ。はては奈落に突き落とされる始末になるかもしれない・・・・。
でも、今少しの冒険なり探索なら、墜落感をおぼえ始め万事に用心を始めた今ならまだ可能かもしれない・・・・。希求のようなもの肯定感のようなものが、またぞろ様々な形をとっては現れては、芽を吹き出そうとする・・・・。
こうして、決断はできず、気持ちは境界線上をあれこれ揺れ動き、何日も振幅の大きな繰り返しを繰り返す。もう牛の反芻だった・・・・。
東京からクーラー・ボックスに入れてキンキンに冷やして持参したビールで、Kと乾杯する。お互い勤め人の頃の習癖が抜けず、「とりあえず、まずビールで・・・」などと言う。グビグビとやる。赤ワインに入るあたりから、時間がマッタリと流れ始める。というか、時間はどこかに消えている。ロープでぐるぐる巻きにして池に沈め冷やしておいた白ワインを少しずつゆっくりと手繰って引き上げる。素晴らしい手応え。ふたりとも自然に口元がゆるむ。豊かな釣果であふれる網を手繰る漁師たちがおぼえる感触もかくや、だ。
Kはスマホでひとり麻雀に興じ始めたらしい。沈黙と闇を通して、麻雀用語が叫ばれる。ちょうどツモった瞬間の声が聞こえた時だった、それを打ち消して、スマホから割り込み電話が鳴る。とたんにKの声が無愛想な調子に急変する。奥さんからの電話だったのか。
到着が大幅に遅れ、釣りができそうもないと判断したKは、キャンプ場に着く前に近くのスーパーで車を停め、鶏一羽の半分を買っていた。それをさばき、燃えさかる焚き火に掛けた大鍋に放り込む。野菜や他の食材もあれこれ入れ、味噌を用意する。いつのまにか 調味料も並べられているが、それも次々に入れてゆく。薪は有料だが、この際焚き火にさかんにくべる。なにしろ焚き火に当たるのは半世紀ぶりなのだ。豪勢に、不意に大きな音も立てて火が燃えさかる。ボッと炎が放電のようにはじけ、火の粉が、時には薪までが四方に撒き散らされる。炎の奥をのぞきこむと、若い木の芽が蛇の舌にような火に舐められ絡みつかれている。湿った焚き木がジューッと湯気を噴き出す。グツグツ煮込まれる鶏鍋からも、火の下に入れた焼き芋アルミホイール巻きからも匂いが広がる。松の木の芳香性樹脂の香りも混じり、火の熱でそれらがまぜられ、混沌となってゆらめく。サイトは木々に囲まれているので、巣がぬくもるような気分になる。日常のこまごまとした気掛かりが消えてゆく。時刻はどうやらテッペンに近づいたらしい。ワインは二本目になり、その白もすぐカラになりそうだ。あたりが温められ、陶然となる。
一瞬、閃光が間をおいて上下に走る。青い矢のようなものが光り、草や水面が鋭利なもので切り裂かれる。いったいな何んだ、この異様な落下と跳躍の素早い動きは。衝撃のあと、沈黙が続く。しかし、水辺で上下に青い光が走った、というただそのことだけで、わたしは即断しようとする。「今のは、水に飛び込み水中で餌を捕獲したカワセミに違いない」、などと思い込もうとする。
ジェージェーという、押し殺したようなしわがれた声がどこかでする。人の声のようにも聞こえる。Kが、「カケスじゃないか」と言う。カケスには物音や鳴き声を真似る習性があり、枝打ちの時の作業音だけでなく、慣れてくると人語まで真似るそうだ。Kは、鳥類図鑑に整然と整理されないような知識を教えてくれる。
火がゆらぎ、身体のなかまで熱が浸み込んでくる。ふだんの日常生活では視覚が酷使されるが、ここでは聴覚やら触覚やら味覚嗅覚といった、視覚に比べれば理知的でない、より原初的な感覚が目覚める。今では、事典によっては人間の感覚は五感あるとはされていない。移動感覚や熱感覚も加えて七感と数えている、などとわたしはまた独りごつ。今感じている気分は、言ってみれば、「異邦感」か。などとそんな表現までひねり出す。
ふたりとも酔いと眠気で、半醒半睡になる。積み上げるようにくべた薪が崩れ、その一本はかなり火から離れた所まで飛んだ。Kがボソッと言う、「いつか薪に山椒魚が潜んでいたことがあってさ。山椒の匂いがする薪があるからヘンだなとは思ったけれど、その薪をそのまま火にくべたんだ。そうしたら、しばらくしたら山椒魚のヤツが一匹、あわてて焚き火のなかから飛び出してきたよ・・・。 山椒魚が火トカゲと呼ばれることがあるのもわかったよ」。酔眼もうろうのわたしは、フォローしようとして元図書館司書の性なのか、既製の知識を披露する、「そうか、火を司る精霊サラマンドルの図像がなんとなく山椒魚に似ているな、とは思ってきたけれど、やっぱりそういうことだったのか・・・・」。

くべてきた薪も尽き、火も燠になり灰になってゆくのを見て、わたしは火吹き棒で燠に息を吹き込む。最後にもう一度炎をかき立てようと思ったのだ。すると、炎ではなく、灰のほうが一気に舞い上がり、燠の高熱にあおられ垂直に巻き上がった。未経験者がやりそうなことだ。
その時だった、焚き火の上に広がって漂う灰のなかに、女性の薄い赤いスカーフのようなものがゆらぐのが見えた。驚いて目をこらす。赤い鳥が一羽音もなく羽根をはばたかしている・・・・。たしかに、赤い鳥だ、幻影とか幻視などではない。残り火が火吹き棒によって突然燃え盛る、その一瞬に灰で煙るなかを、赤い鳥、そう・・・火の鳥が舞い上がったのだ。炎が生き物のようにゆらめき、飛翔する、火に輝く、火の鳥だった。
だが、その鳥の影はすぐに消える。私はすぐに火吹き棒を握り、燠をかき混ぜる、顔が火照るにもかかわらず炎をかき立てようとする。火花がほとばしる。熱風で巻き上がる灰のなかに垣間見た火の鳥を追い、か弱い手でもってその鳥をつかまえようとした。
しかし、火の鳥はどこか闇に消え、驚異の美しい鳥は二度と出現しなかった。あれは人間にはかない望みとか憧れを抱かせる、たんなる偶発的な火のいたずらだったのかもしれない。しかし、一瞬味わった突き上げてくる高揚感をなんとかしてすぐに再現しようとして、わたしは食べ残した鶏の骨を数本火に放り込む、コップに残っていたワインも。しかし、鳥がふたたび飛翔することはなかった。火の鳥を再現させようとする試みも徒労に帰し、わたしはただ虚しい思いを噛みしめるばかりとなった。
衰える火と冷めてゆく大鍋を前にしながら、わたしは幻の火の鳥を夢想のなかで追った。火に掛けられている大鍋なら鳥の居どころを教えてくれるかもしれない。そうなのだ、こんな神話があるはずだ ― 鳥が飛んできて、大鍋に入っている秘薬を飲むと、その鳥は自在に再生できる身に変身する。そしてその鳥は大鍋に入っている生の秘薬を人びとにわかち与える。こういった神話が北欧神話にたしかあるはずだ・・・・。この神話には大鍋の上を飛んだ火の鳥の行方を探るヒントが隠されているはずだ。
きっとKのことだ、先程から焚き火を前にしたわたしの様子がおかしいことに気づいているはずだ。わたしの奇妙な動きをどうKに説明しよう。そうだ、持参した志賀直哉の短編「焚き火」に書かれていることと同じことをしようとしていただけなのだ、と言おう。挙動不審だったのも、「焚き火」で主人公が行った行為を自分でもやってみようと思い立ったからだ、と。そのうえで掌編小説の該当するその箇所を数行Kに読んでみよう ― 「Kさんは勢いよく燃え残りの薪を湖水へ遠く抛った。薪は赤い火の粉を散らしながら飛んで行った。それが、水に映って、水の中でも赤い火の粉を散らした薪が飛んで行く。上と下と、同じ孤を描いて水面で結びつくと同時に、ジュッと消えてしまう。そしてあたりが暗くなる。それが面白かった。皆で抛った」。志賀直哉の充実した創作期の文だ。忠実な写実文のようだが、平板なありきたりの描写ではない。背後の闇のどこかに神秘が潜んでいるようで、緊迫感が伝わってくる。これからふたりで志賀直哉の主人公と同じことをやってみないか、とKに持ちかけてみよう。
Kはすぐに同意する。ふたりは燃え残りの薪を池のほとりまで運び、暗い水面に向かって一本一本投げ入れた。たしかに、赤い火の粉が空中と同時に水中を、孤を描いて飛んでゆく。暗闇のなかで火の粉はすぐには消えない。花火のように広がる火の粉が闇に何かを照らし出すことを期待した。飛んでゆく火の粉に並行するようにして、音もなく火の鳥が飛ぶのではないか・・・・。
翌日、昼前になってキャンプ地を後にした。峠まで上り、そこから谷間のキャンプ地を鳥瞰するようにふりかえった。雑草などが刈り取られ、広く平らに整備されたキャンプ場は遠く上から見るとまるで緑の飛行場だった。点在する色鮮やかなテントや車がかすかに差し込む陽を浴び、それに呼応するかのようにそれぞれに煙も立て、動き始めていた。きっと音も立て始めているはずだ。「未確認飛行物体たちだな、これは」と、K。しかし、わたしには離陸しようとしている未確認飛行物体群がメカニックなものには見えなかった。人が住みこみ、生活がいとなまれるものだった。かすかではあるが生気が通うものだったし、生き物の気配がするものだった。
やがて雲間から一条の光が漏れ、その光はキャンプ地の中の島に当たった。霧のかかる山間を、光は上から断固として中の島を指し示し続けた。小さな中の島は陽の光でたちまち赤く染まった。水面に顔を伏せたような中の島の木々が風に吹かれ、木々がそよいでいるように見えた。一瞬、中の島がかすかに動いたように見えた。中の島がうずくまる火の鳥に変貌しようとしている・・・・。まだ、わたしは火の鳥に執着している、探している・・・。
東京に帰ったあとでも、夜になるとKに返し忘れたヘッド・ランプを頭に装着し、狭いマンションの照明を消しテレビを消してかろうじて得られる暗闇のなかをうろつくことがある。ひょっとして鳥が部屋の片隅にでも隠れているのではと思いながら。鳥を探して、火の鳥を・・・。
しかし、さすがに体験からわきまえるようにはなっていた ― 苦難に満ち、危険にさらされる長い長い遍歴や流離を繰り返さないといけないのだ。火の鳥が突然姿を現し、それに遭遇するためには。